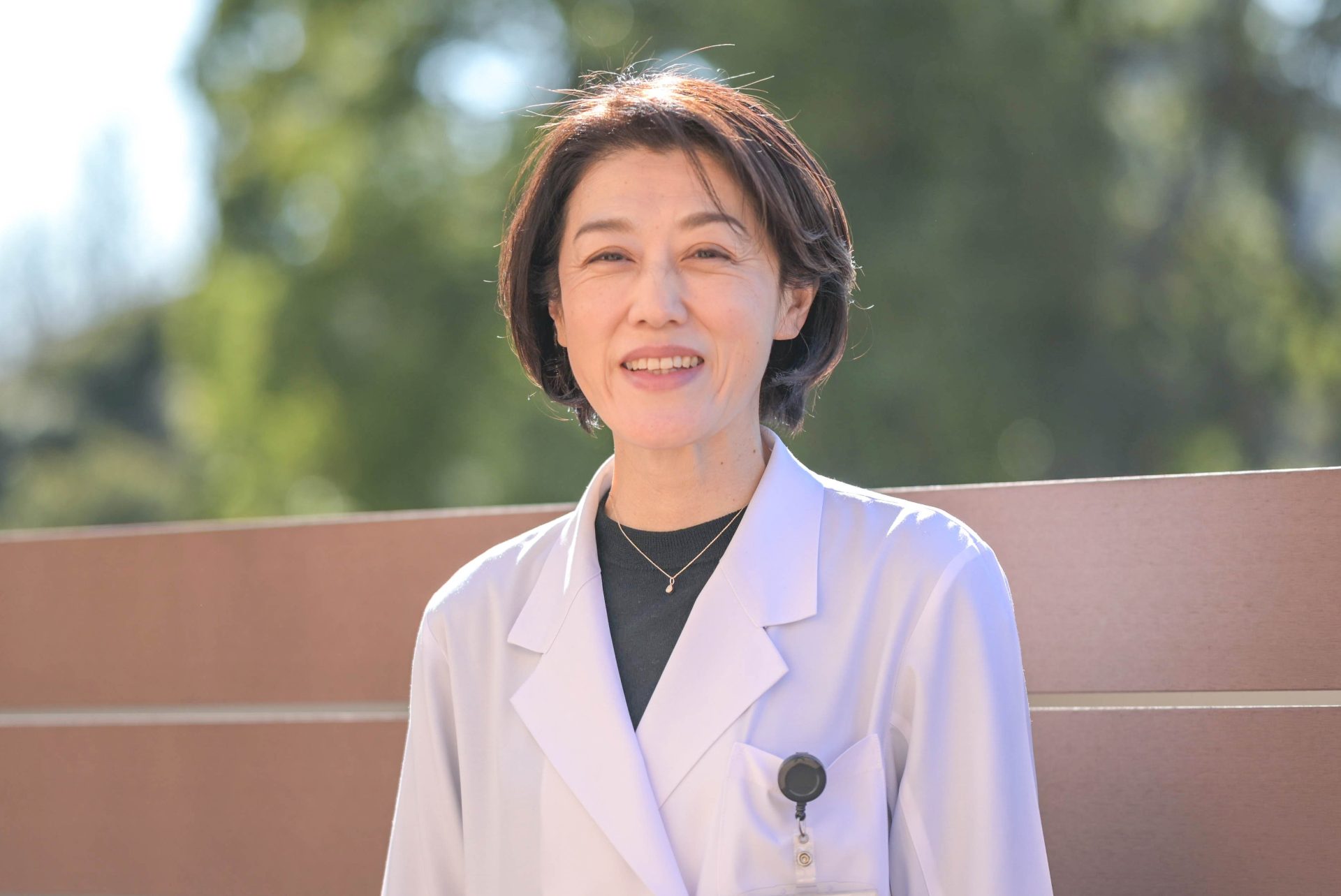小児精神保健科
-
小児精神保健科
について 小児精神
保健科
について - 診療内容 診療内容
- 医師のご紹介 医師のご紹介
最新の診療法で
こころの問題を
幅広くサポート
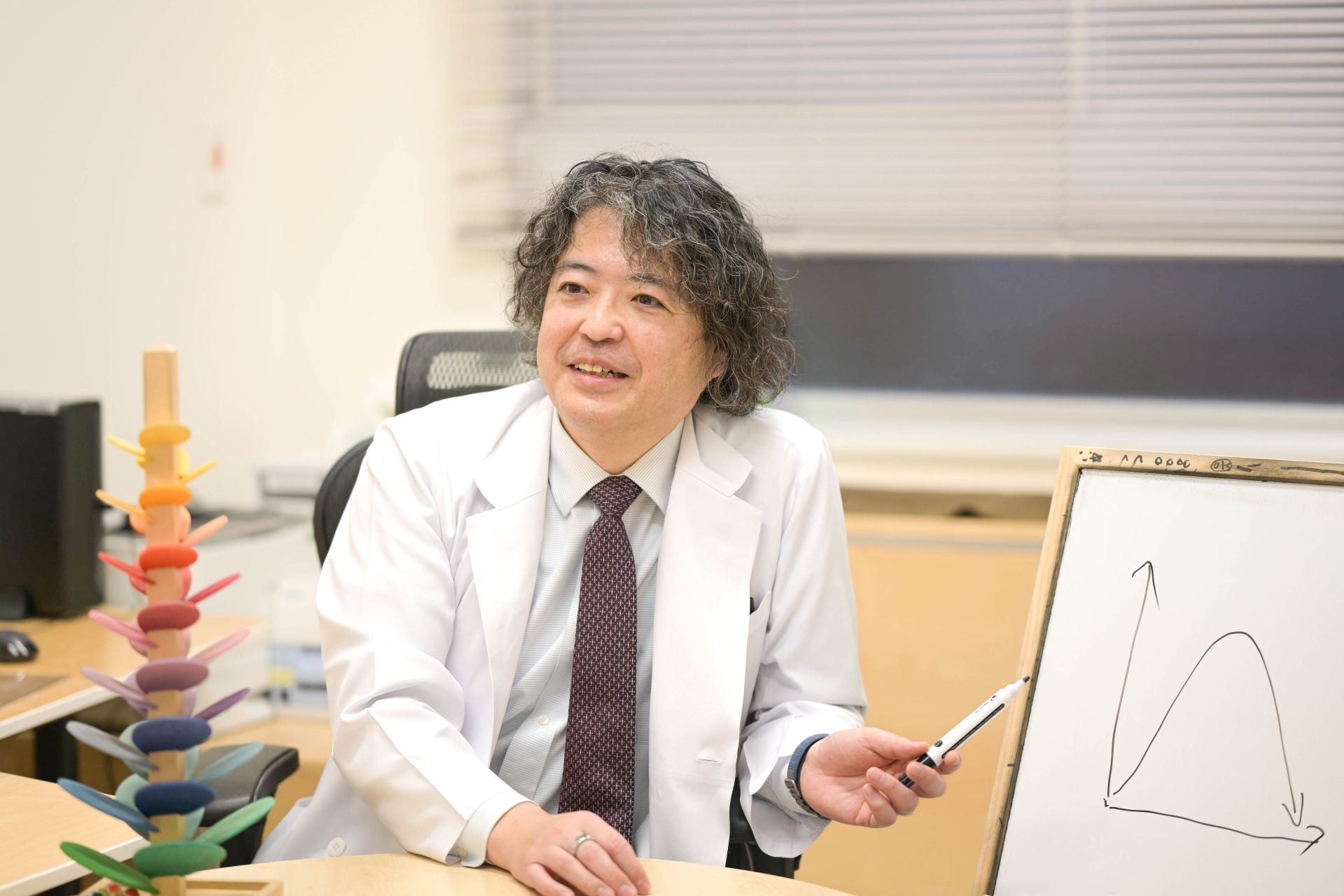
児童・思春期専門の精神科医がお子さまの「こころの問題」を診療します。 ⾃閉スペクトラム症や注意⽋如多動症、限局性学習症に代表されるいわゆる「発達特性の偏り」、不安症状や気分の落ち込み、潔癖症状、不登校といった「⼦どもの情緒の問題」、さらにはチック症状や睡眠の問題といった「⼦どもの習癖」まで幅広く相談をお受けしています。
-
一般外来と特殊外来予約費を要する外来について
当科は、児童・思春期専門の精神科医がお子さまのこころの問題にあたる一般外来と予約費を要する外来(初診及び親子相互交流療法(PCIT)を含む特殊外来)から成っています。はじめに外来において医師の診察を行った後、治療の方針を提案させていただきます。支持的な関わりを基本とし、必要に応じた各治療プログラムを進めてまいります。明らかな「精神障害」だけでなく、その周辺にある状況の改善にも関わり、予防的な役割も果たしたいと考えています。

-
子どものこころ相談室と治療プログラム
併設の「⼦どものこころ相談室」で、公認⼼理師・臨床⼼理⼠による⼼理検査やカウンセリング、⼼理教育などを行います。特別に設定した各種治療プログラムも、⼦どものこころ相談室にて行います(PCITとPEERS®を除く)。詳しくは以下をご覧ください

-
- 遊戯療法(プレイセラピー)
概ね3歳から11歳までの子どもを対象とした心理療法の一種で、「遊び」を軸としたセラピーです。⼦どもの精神療法の代表的な技法の⼀つです。
遊戯療法の適応となる精神疾患は多様ですが、まだ⾔語的な交流が難しいお⼦さまの問題、不安症などが中⼼となっています。

-
- 認知⾏動療法
「遊戯療法」よりもやや年⻑の⼦ども向けの精神療法です。⼦どもが症状を呈するに⾄った認知(考え⽅)のパターンや⾏動のパターンなどを、遊びの要素を加えながら洞察し、必要に応じて修正していく⼿法と⾔えます。基本的にはある程度の回数を区切って進めていきます。当科での主な対象は、不安症、恐怖症、強迫症、トラウマ関連障害としています。特に⼦どものトラウマ治療の第⼀選択とされているトラウマフォーカスト認知⾏動療法(TF-CBT)や、強迫症への曝露反応妨害法(E/RP)などは積極的に取り組んでおります。

-
- ペアレント・トレーニング
⽶国カリフォルニア州ロサンゼルスにあるUCLA 神経精神医学研究所で開発された、ADHD(注意⽋如多動症)を持つ⼦どもの親に対するアプローチです。ADHD の特徴を理解し対応の仕⽅を学ぶことで、悪循環を抑え良好な親⼦関係を育むことを⽬的としています。当科では、1 回の参加者は6〜8 名とし、会期中にメンバーを固定した少⼈数クローズドグループで隔週90 分の11 回プログラムを⾏っています。⽗親のみのグループはより少ない回数で実施しています。

-
- PCIT(親⼦相互交流療法)
⽶国フロリダ⼤学のEyberg⽒によって考案・開発された⾏動療法の1つです。親⼦間の関係の強化と養育者の適切な命令の出し⽅の⼆つの柱を中⼼概念としており、そのために親が⼦どもに直接遊戯療法を⾏い、治療者は別室からビデオカメラを通して親にライブコーチングするという点が特徴的です。1 セッションの⻑さは1 回60〜90 分で、通常12〜20回程度で終了となります。

-
- CARE(⼦どもと⼤⼈のきずなを深めるプログラム)
⽶国オハイオ州シンシナティ⼦ども病院のトラウマトリートメントトレーニングセンターで開発された、⼦どもと関わる⼤⼈のための⼼理教育的介⼊プログラムです。上述のPCITの理論や枠組みに基礎を置いていますが、経済的・時間的制約は軽減されています。⼼の問題を抱えたお⼦さまへの対応だけでなく、⼀般的な⼦育てにも応⽤できるスキルの多いプログラムです。会期中にメンバーを固定した少⼈数クローズドグループで1 回の参加者は最⼤でも6〜8 名とし、全5 回のプログラムを⾏っています。

-
-「安⼼感の輪」⼦育てプログラム
アタッチメント研究に基づいて開発され海外では介⼊効果も実証されているCircle of Security という親⼦関係⽀援プログラムをベースにしています。 わかりやすい映像や図表を盛り込んだDVD 教材なども⽤いて進めていき、プログラムを通して親⼦関係への洞察を深めていくことを⽬指しています。 親⼦関係に焦点づけた⼼理教育プログラムと⾔えます。基本的には個別で実施しており、1 回90 分、全8 回のプログラムになります。

-
- ペアレント・クラス
子どもの⼼の発達経過を、乳幼児期(0 歳〜5 歳)と思春期(10 歳〜17 歳)の⼆つの年代に焦点を当てて学ぶ、親を対象とした⼼理教育プログラムです。 乳幼児期は親からの分離~個体化過程とアタッチメントの発展という観点から、思春期は前進と後退(幼児返り)を繰り返しながら進⾏する⼼理的⺟親離れと⾃分作りという観点から⼼の発達を⾒ていきます。

-
- PEERS®(外部の⼤学にて共催の形式)
PEERS® (Program for Education and Enrichment of Relational Skills)とは、⽶国UCLA の研究者Laugeson ⽒によって思春期の⾃閉スペクトラム症や社会性に課題のある⼦ども達に向けに作成されたプログラムです。認知⾏動療法理論と保護者のサポートを基本原理としており、グループで取り組みます。カリキュラムは、社会適応に重要な役割を果たす“友達作り”と、その良い関係を維持していくために必要なスキルに焦点を当てられています。全14 回のプログラムとなっております。

-
小児精神保健科部長 小平 雅基
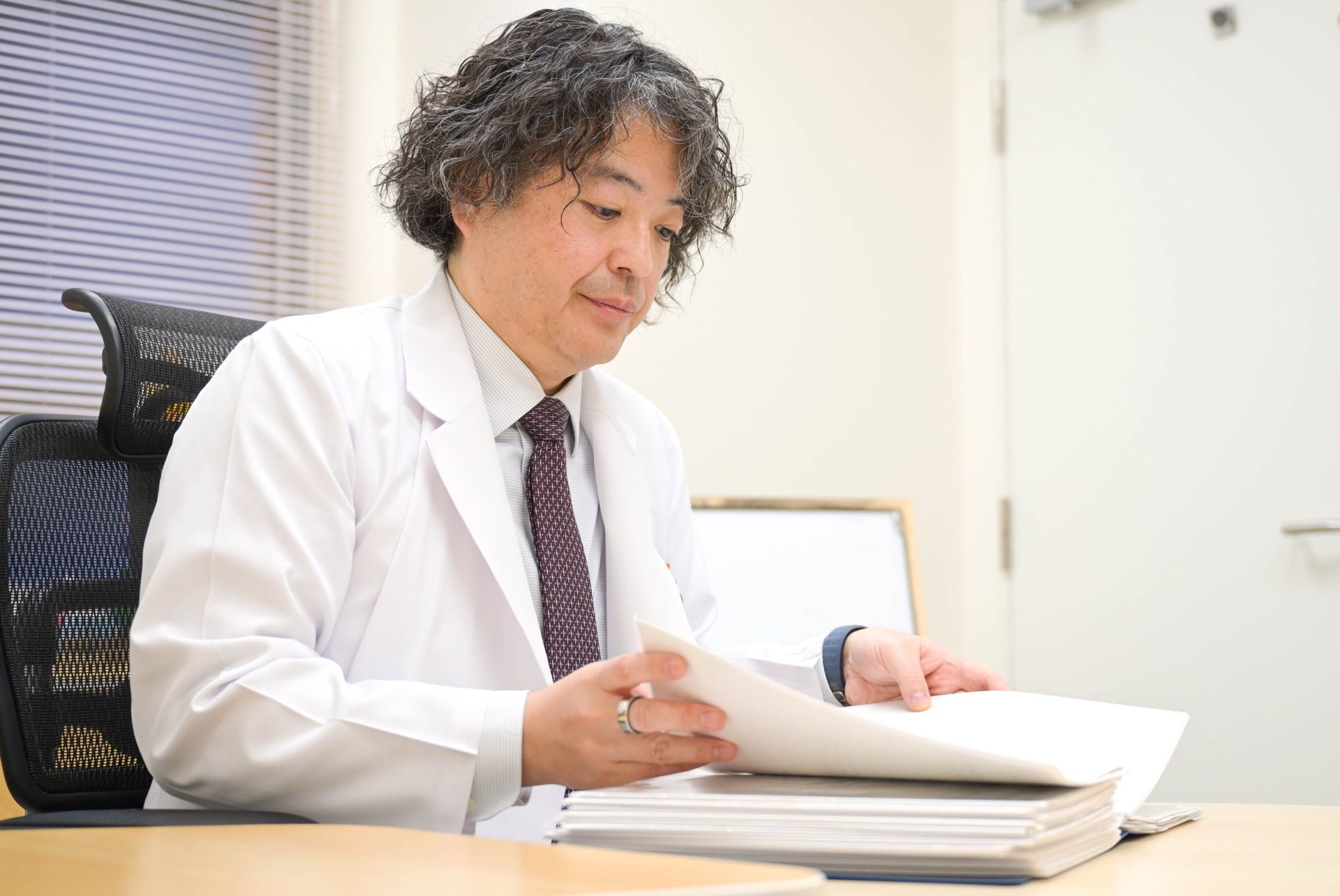
- 専門分野
- 子どものこころ専門医
日本児童青年精神医学会常任理事・認定医
精神保健指定医
日本精神神経学会専門医
日本トラウマティック・ストレス学会
日本子ども虐待防止学会
日本認知療法学会
TF-CBT LC研究会運営委員長
PCIT International認定機関内トレーナー など
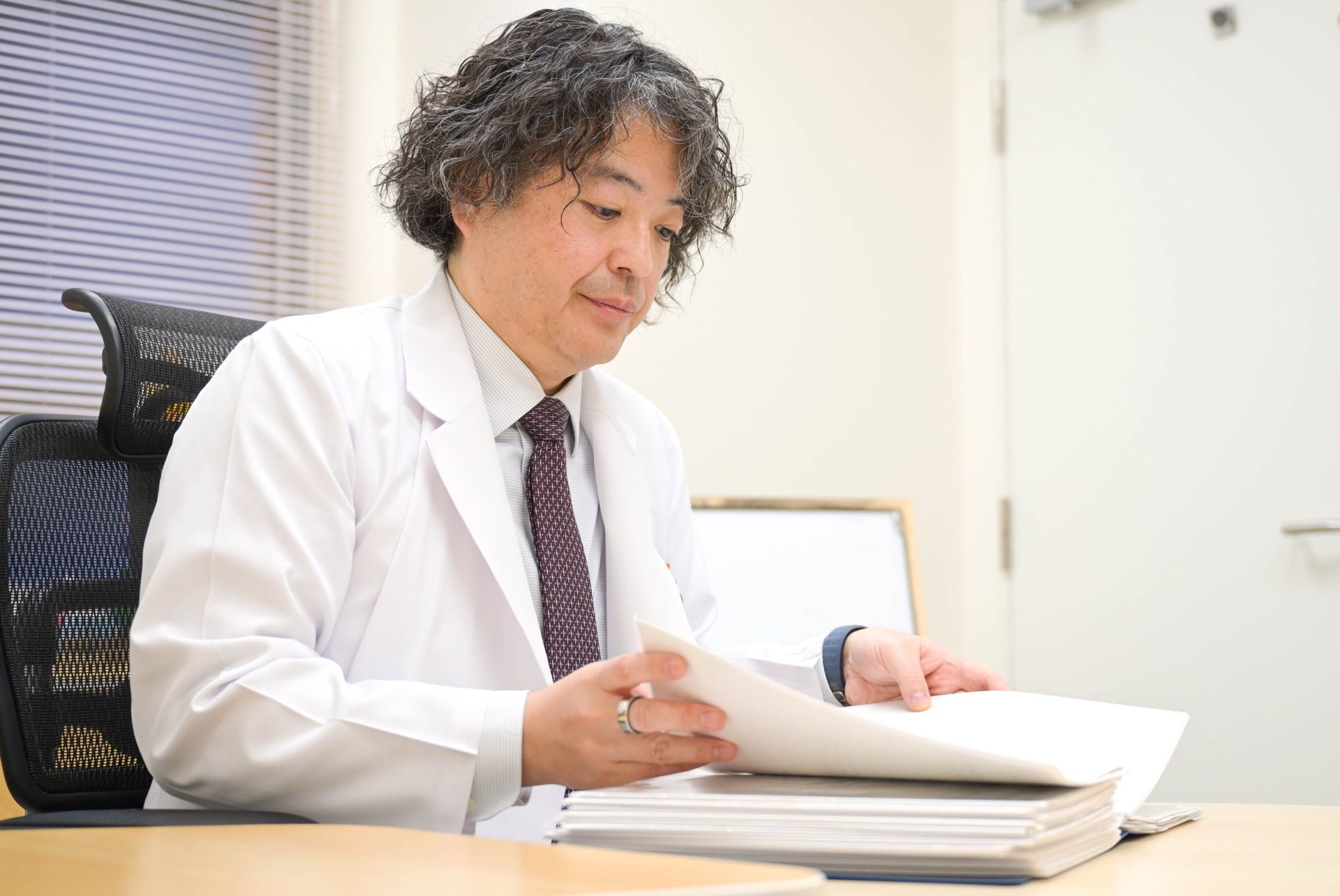
-
小児精神保健科副部長 細金 奈奈

- 専門分野
- 子どものこころ専門医
日本児童青年精神医学会認定医
精神保健指定医
日本精神神経学会専門医
日本乳幼児医学・心理学会評議員
日本トラウマティック・ストレス学会
PCIT-Japan理事
CARE-Japan監事
PCIT International認定機関内トレーナー
CAREファシリテーター など